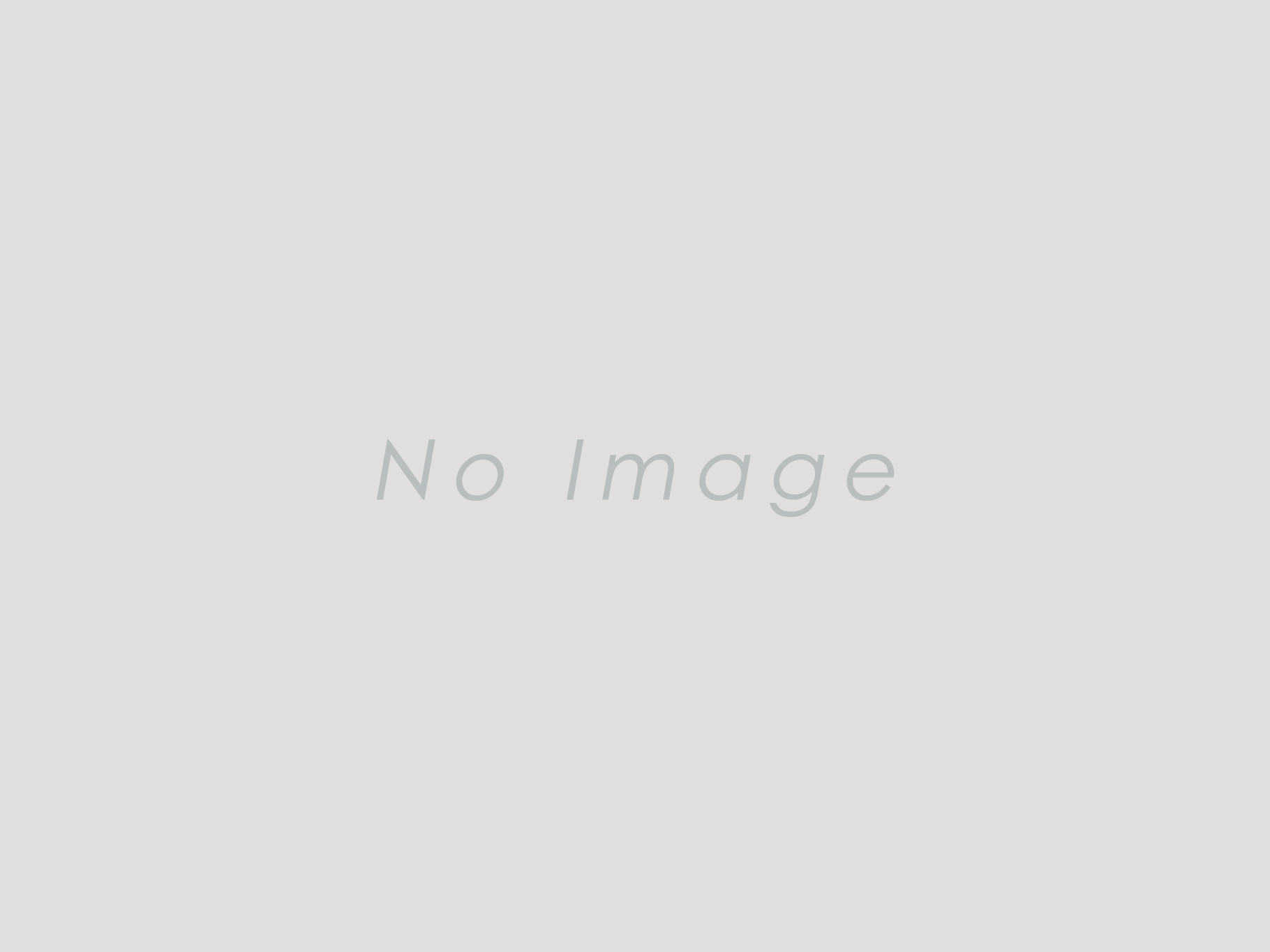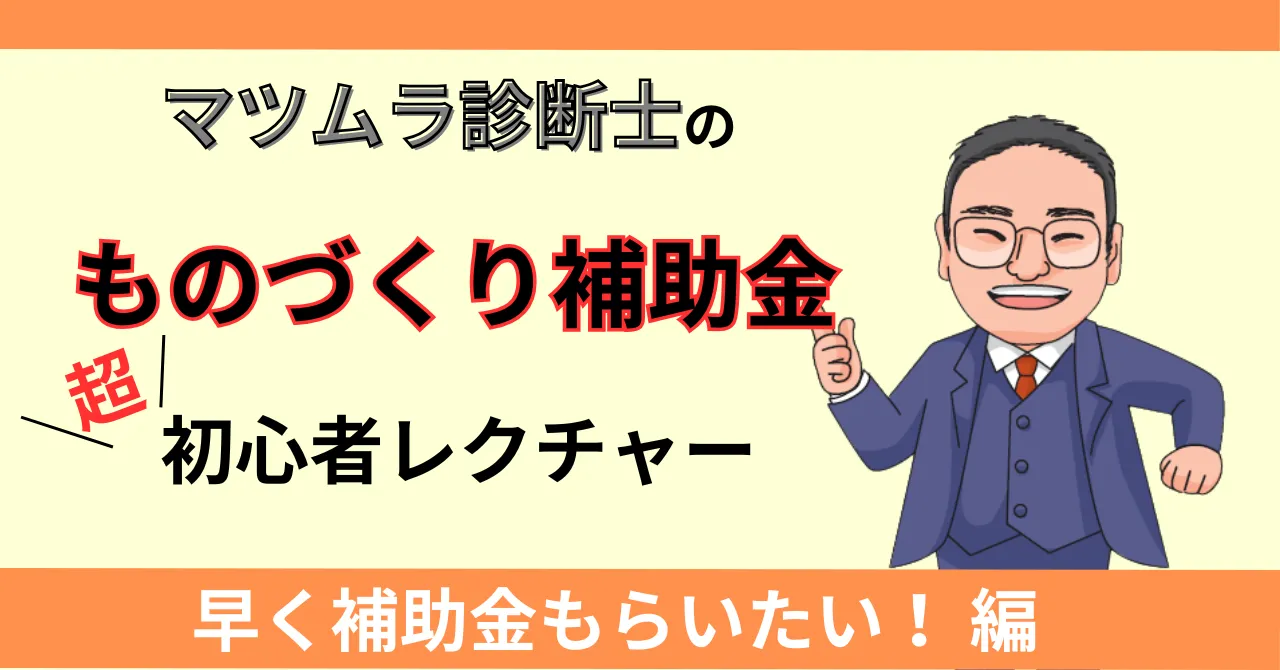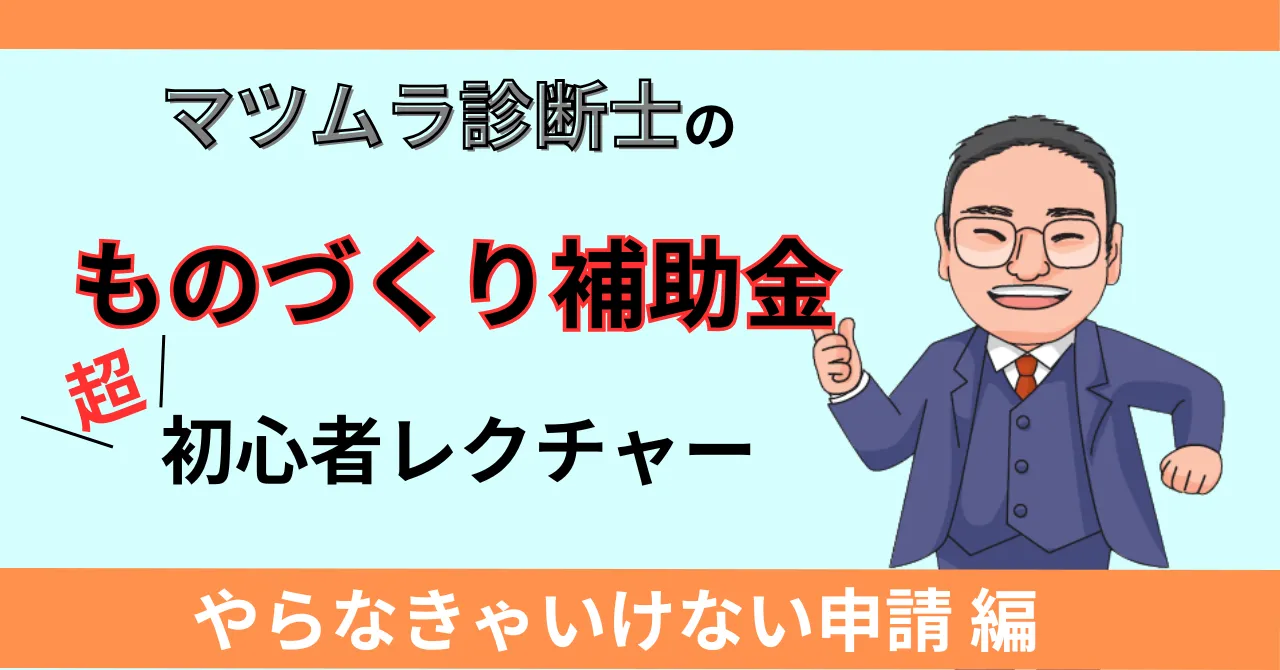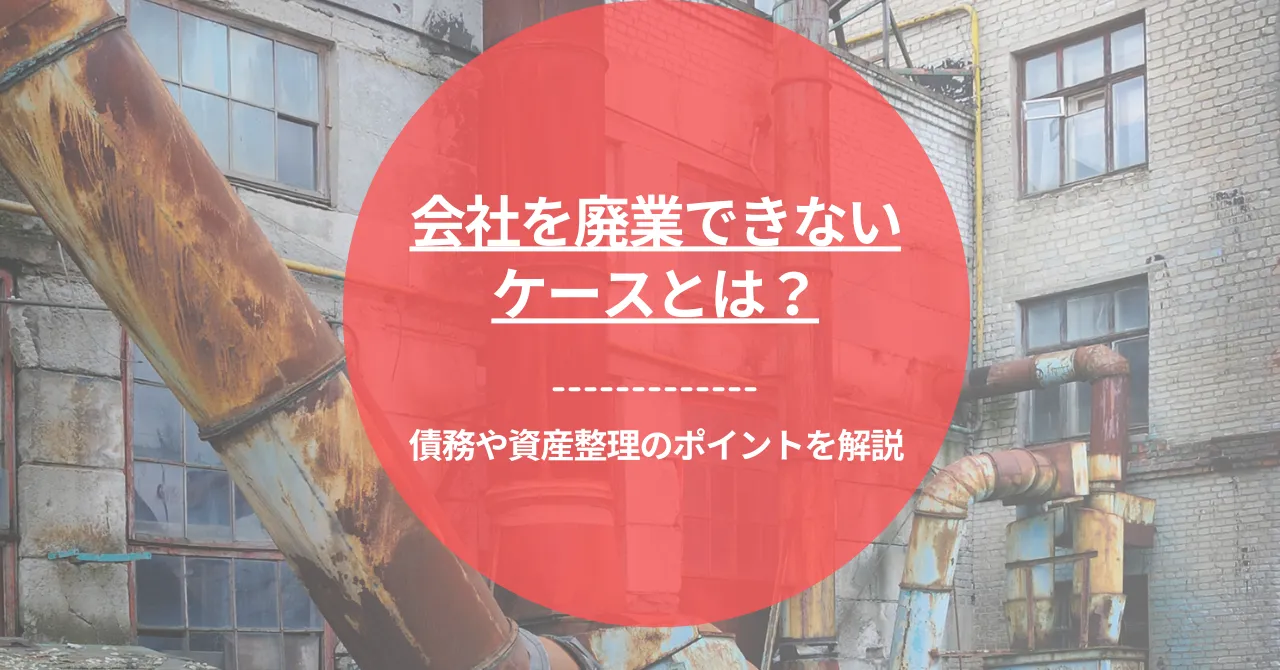事業承継で欠かせない遺言の活用法とは?作成のポイントと注意点まとめ
2024/10/20
経営者が高齢で、将来的な事業承継に備えて検討すべきなのが遺言です。
遺言をうまく活用することで円滑な事業承継が行える一方、下手を打つと親族に禍根を残す事態を招きかねません。
本記事では事業承継で欠かせない遺言に着目し、活用のメリットや遺言をしなかった場合の影響などを解説します。
この記事を書いた人
松村昌典
株式会社エムアイエス 代表
山口県山口市(旧:阿知須町)生まれ 立命館大学経済学部卒業
大学卒業後、山口県中小企業団体中央会に入職。ものづくり補助金事務局を9年間担当。
2022年5月に独立し、株式会社Management Intelligence Service(現:株式会社エムアイエス)を立ち上げる。経営コンサルタントとして支援した企業はのべ1,000社以上。ITやマーケティングに関する知見の深さと、柔軟な発想力による補助金獲得支援に定評がある。自らのM&A経験を活かした企業へのM&A支援も得意とする。
「山口県から日本を元気にする経営コンサルタント」を合言葉に、山口県内の企業はもちろんのこと、県外企業へのコンサルティングも積極的におこなっている。
〈保有資格・認定〉
中小企業診断士
応用情報技術者
〈所属・会員情報〉
山口県中小企業診断士協会 正会員
山口県中小企業組合士会 正会員
山口県中小企業家同友会 正会員
目次
事業承継で遺言を活用するメリット
事業承継を行う際に遺言を活用するメリットは、大きく4つに分けられます。
遺言をせずに死亡したら事業承継にどう影響する?
仮に遺言書を作らずに経営者が死亡した場合は、遺産分割協議が発生します。遺産分割協議は法定相続人全員の合意が必要なため、お互いが権利を主張し、一歩も譲らなければ、いつまで経っても終わりません。
しかし、法定相続人に与えられた権利を最優先して、機械的に分割すれば、自社株も同様に分けられてしまいます。円滑な事業承継に欠かせない自社株・資産がバラバラになり、資産を集めることが難しくなるでしょう。
事業承継をうまく行うことができず、場合によっては事業継続が厳しくなります。
先代の経営者が自分が亡くなってからの青写真を描いていた場合には、遺言を残した方が賢明です。
事業承継に活用できる遺言の種類
事業承継において活用できる遺言には、大きく分けて2つの種類があります。
ここでは2種類の遺言についてまとめました。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者自らが作成できるものです。大きな特徴は、「遺言の本文」「作成日時」「遺言者の氏名」「押印」があれば、遺言として認められる点です。
自筆証書遺言は思い立ったその日に作成できるほか、作成に費用がかからず、法務局にも安価で保管してもらえます。
一方で、遺言書を悪用したい相続人が遺言者が作成したものを偽造し、自分に有利な内容に書き換える可能性もあるでしょう。
また、せっかく遺言書を作ったのに発見されなかったという事例もあります。
被相続人が亡くなった場合、法定相続人は家庭裁判所において検認手続きを行うなど、面倒な部分があるのも事実です。
とはいえ、ここ数年で自筆証書遺言が活用しやすい環境が整えられており、自筆証書遺言でも十分効力を発揮し、効果的に活用できる時代になってきました。
公正証書遺言作成の流れ
公正証書遺言を作るのに何が必要で、どんなことをしなければならないのか、事前に知っておくと準備もしやすいでしょう。
ここでは、公正証書遺言作成の流れを段階ごとに解説します。
- 必要書類の準備
- 遺言内容の検討
- 証人・遺言執行者の選定
- 公証人役場で遺言作成
- 遺言者本人の印鑑登録証明書もしくは公的期間が発行した顔写真付き身分証明書
- 遺言者と法定相続人の続柄などが記された戸籍謄本など
- 法定相続人以外への遺贈の際には、その人物の住民票など
不動産を相続させる場合には登記簿謄本や固定資産評価証明書などが、預貯金の場合には預貯金通帳などが別途必要になります。
- 作成時未成年の人物
- 法定相続人に該当する人物
- 受遺者
- 法定相続人や受遺者に該当する人物の配偶者など
遺言によって財産を受け取る可能性がある人物や法律的に責任能力が認められない人物などは証人になれません。
一方で証人は公証役場などが用意するケースもあります。
遺言執行者は、遺言に書かれた内容を実現させていく人物です。遺言執行者には未成年者や破産者でなければ誰でもなることができるため、法定相続人なども遺言執行者になれます。
しかし、よりスムーズな相続・事業承継を考えると、法律事務所の弁護士などに依頼した方が問題は起こりにくく、トラブル防止につながるでしょう。
遺言による事業承継がおすすめの経営者
事業承継をする際に、遺言を残した方がよいケースがあるのが実情です。
ここでは、遺言での事業承継がおすすめな経営者を解説します。
遺言作成の際に注意したいポイント
最後に遺言作成の際に注意しておきたいポイントについて解説します。
遺言書の作成後、亡くなってから取り扱いを巡り面倒なことにならないよう、想定される注意点を把握した上で作成しましょう。
費用はかかりますが、弁護士など専門家に相談することでトラブル回避につながります。自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、弁護士への相談は可能です。
参考:遺言書の作成方法と弁護士に依頼する際のポイントを解説|カケコム(事業対象:法律 事務所:東京都港区六本木5-9-20)
まとめ
先代経営者の遺産を巡って親族間でトラブルになるほか、誰が経営権を握るかでも「お家騒動」になってしまうことがあります。
円滑な事業承継のためには遺言書の作成が欠かせません。そのうえで、しっかりと効力を持たせるために、弁護士など専門家に相談をしながら、トラブルになりにくい形を目指していくことが大切です。