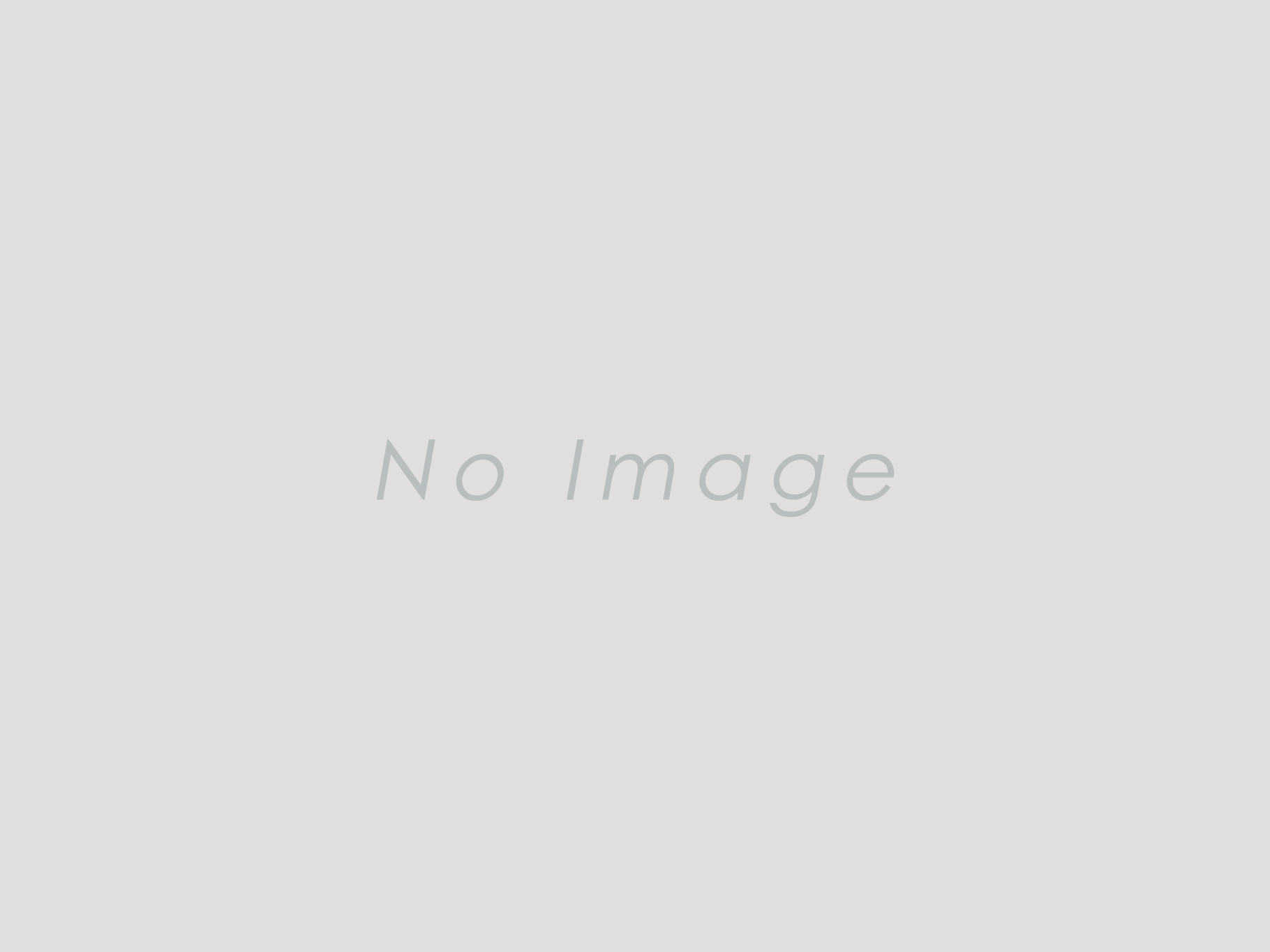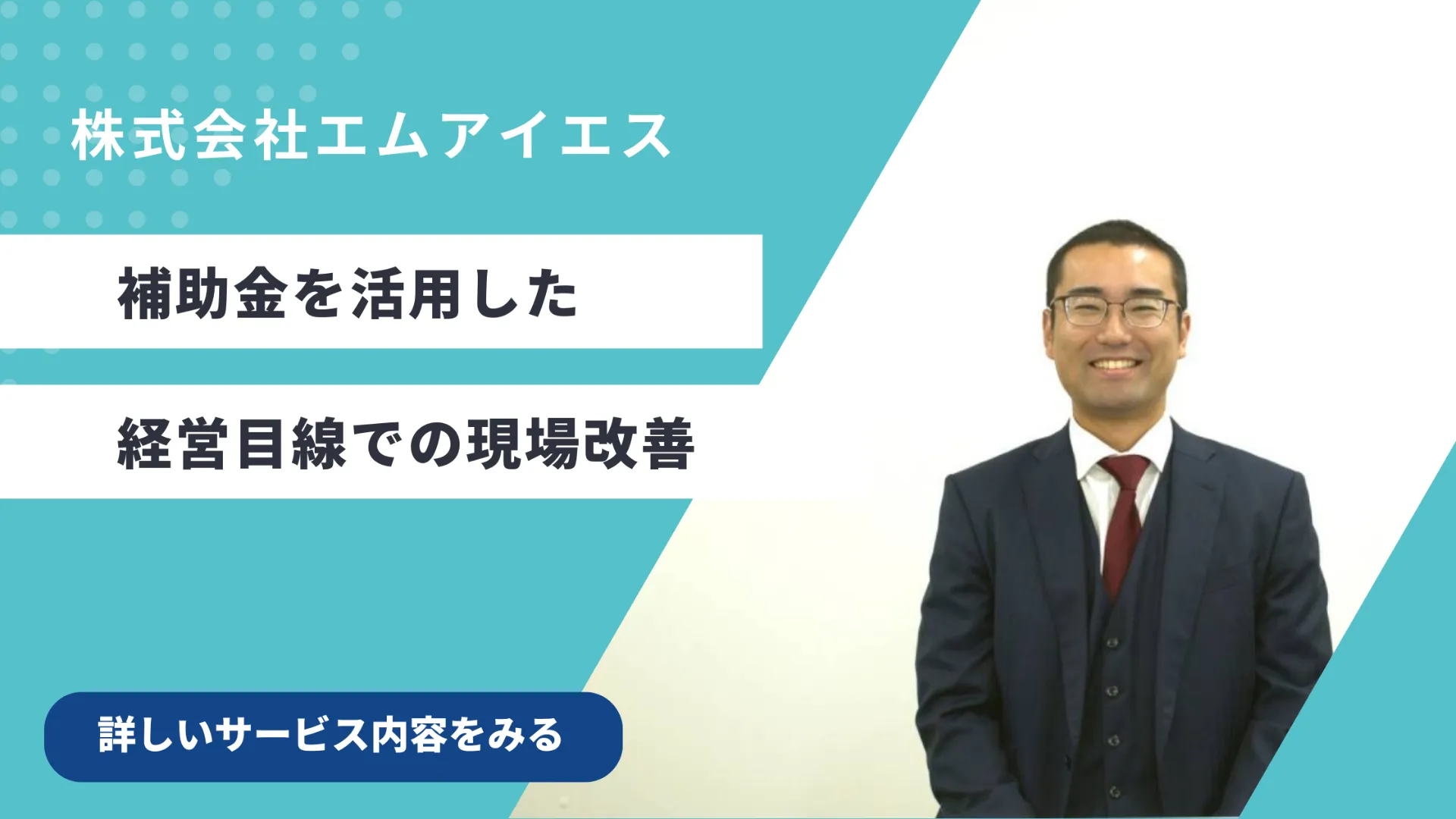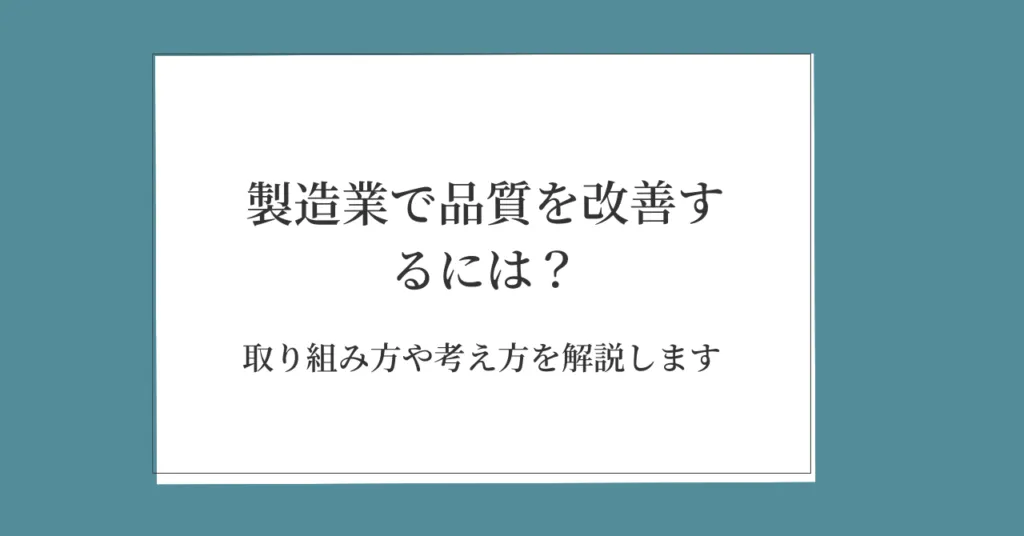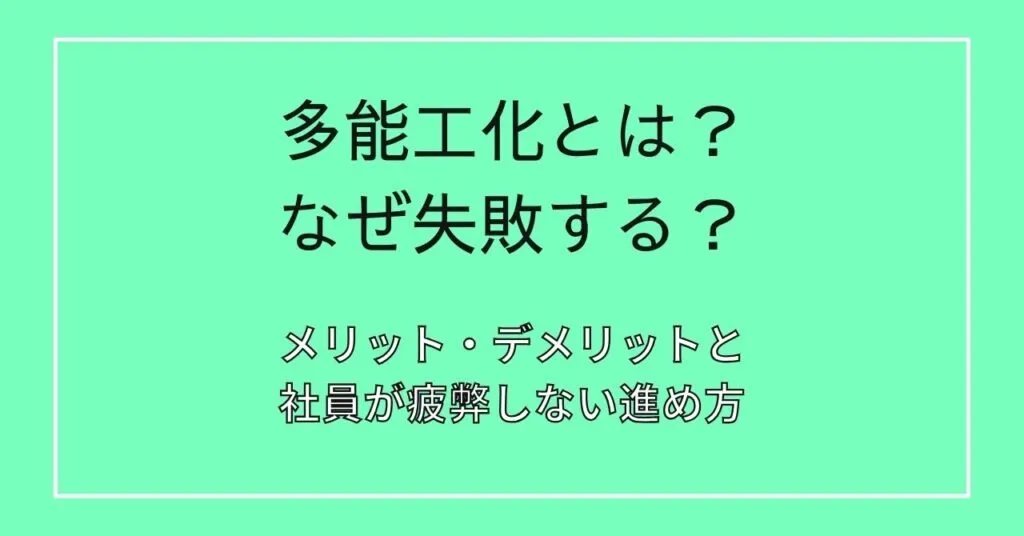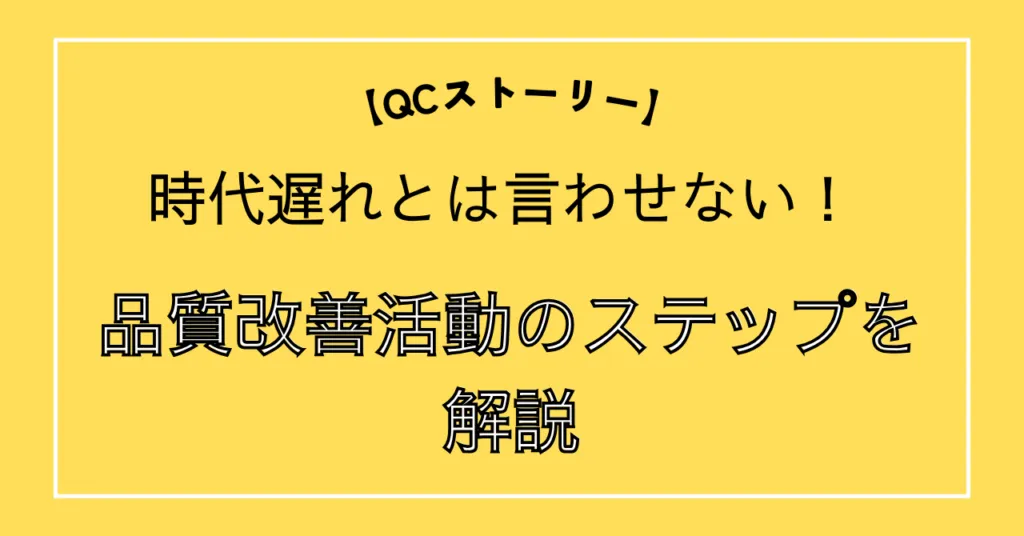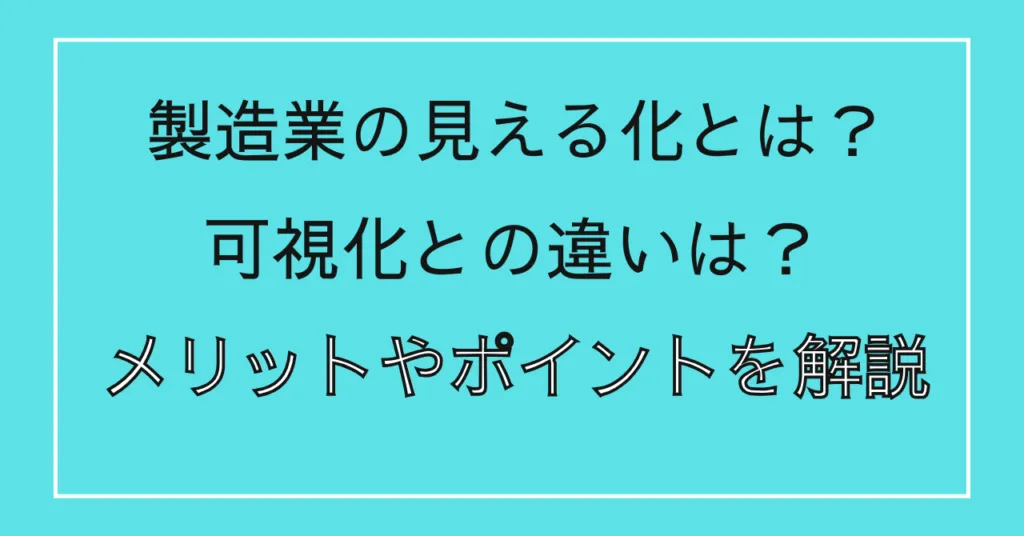製造業の見える化とは?可視化との違いは?メリットやポイントを解説
2023/11/062025/02/19
最近「見える化」という言葉をよく見かけませんか?新しい言葉にみえますが、発祥は1998年にトヨタ自動車の岡本渉氏が発表した「生産保全活動の実態の見える化」という論文です。
キャッチーな響きも相まって様々な分野で使われるようになりましたが、言葉の広がりとは裏腹に、本当の意味や目的を知っている人は少ないのではないでしょうか。この記事では「見える化」についての疑問点を徹底解説します。
目次
見える化の目的とメリット
見える化はトヨタの改善活動の中から発生した言葉で、「状況を常に見える状態にしておき、問題を即座に明らかにできる状態にし、迅速な問題解決を行う」ことを意味します。ここでは見える化を行う目的やメリットを説明します。
見える化の具体例
見える化について分かったものの、自分の職場でどのように見える化に取り組むべきかピンとこない方もいるでしょう。ここでは見える化について具体的な例を用いて説明します。見える化に取り組む上で参考にしてみてください。
あんどんによる異常事態の見える化
「あんどん」とはトヨタ生産方式のひとつで、もともとは異常に気付いた社員がスイッチを押すことにより点灯するランプのことでした。現在ではランプが電光掲示板に変更されており、より分かりやすく異常を知らせるシステムとなっています。
異常を即座に知らせることは見える化において非常に重要です。どの職場も全く同じシステムを採用するのは現実的ではないため、それぞれの職場に適した異常発生時の迅速な周知システムを検討しましょう。
参照:トヨタ自動車「トヨタ生産方式|詳細解説‐柱‐」
見える化を実現する4ステップ
見える化にあたって重要なのは、取り組む手順です。適切な手順を踏まずに見える化を行っても効果は出づらいです。ここでは実際に見える化を行う手順を解説します。
2.見える化が可能な環境を構築する
見える化が可能な環境を構築するにはDX化が非常に有効です。デジタルを利用することで正確な見える化が可能となるためです。様々なシステムやIoTデバイスがあるため、目的に沿ったものを選びましょう。
もし社内にITに詳しい人材がおらずDX化が難しい場合は、外部コンサルティング会社に相談をするとよいでしょう。ただ、システムやIoT機器を導入すると不具合時に対応する必要があるため、見える化の取り組みを機に社内でIT人材を育成するきっかけにしてはいかがでしょうか。
しかし、IT技術が使えなくてもアナログな方法で見える化をすることは可能です。どうしてもIT技術を導入できない場合は、現場の知恵と工夫で見える化が可能な環境をつくりましょう。
見える化を行うポイント
見える化を行う上で重要なポイントを解説します。
「見せる化」にならないようにする
「見せる化」とは、業務に関するデータをいつでも確認できる状態にすることです。メリットとしてデータ収集やモニタリングが容易になることが上げられますが、見える化と違ってパソコンなどを開かないと見えない状態なので、意図しないと見ることができません。そのため、状態や不具合を瞬時に知らせることはできず、見える化と比較すると生産性向上には劣ります。システムやIoTを導入する際は、見せる化で終わらないか注意して選びましょう。
必ずしも見せる化が悪いわけではありません。見せる化された資料は、分析作業や研修、外部発表では非常に有効です。見える化と見せる化の違いを理解し、データや資料を適切に運用しましょう。
見える化についてよくある質問
最後に、見える化についてよくある質問を集めました。見える化に取り組む際に参考にしてください。
見える化と可視化の違いってなんですか?
日本にはもともと可視化という言葉があり、見える化という言葉に違和感を持つ人も多いようです。しかしその意味は異なります。
広辞苑には可視化の意味は載っていませんが、可視とは「肉眼で見ることができること」となっています。そのため可視化とは肉眼で見られる状態と定義できます。見える化は広辞苑によると「〔俗〕企業活動などで、現場の問題点などを客観的に把握できるように視覚化すること」となっており、問題解決のために視覚化するという意味合いがあります。また俗語であるため、定義があいまいなのは否定できず、製造業以外ではしばしば混同した使われ方をされているのも事実です。しかし製造業においては、見える化という言葉の独自の意味が重要となるため、区別して使いましょう。
正しい「見える化」で生産性をアップさせよう
製造業から始まった見える化ですが、現在では医療やサービス業など様々な分野で使われています。しかし本当の意味を理解していないために、効果的な見える化ができていない場面があるのも事実です。
見える化の肝は、自動的に、勝手に目に入る状態をつくることです。
見える化を理解して、業務効率化と生産性向上につながる取り組みをしてほしいと思います。
株式会社エムアイエスの現場改善コンサルティングサービスは、大企業で現場改善歴30年以上のベテランコンサルタントが企業に出向いてアドバイスを実施します。
中小企業診断士が在籍しており、ただ現場改善をするのではなく、経営目線で役に立つ施策提案が強みです。
補助金獲得サポート経験も豊富にあるため、多くのケースで補助金・助成金を活用して費用を抑えることが可能です。
現場改善を検討しているけれど費用面でお悩みの方は、ぜひご相談ください。