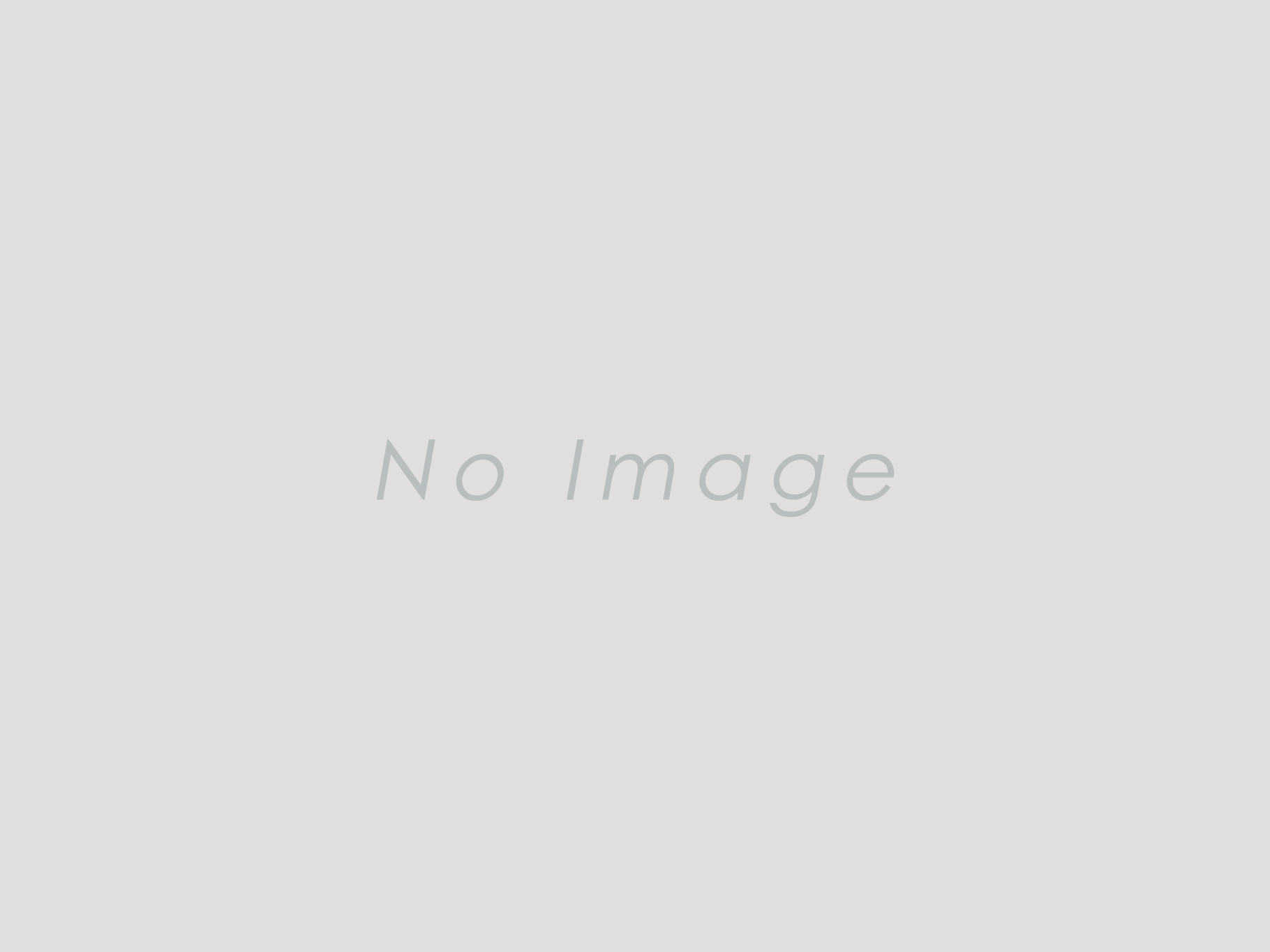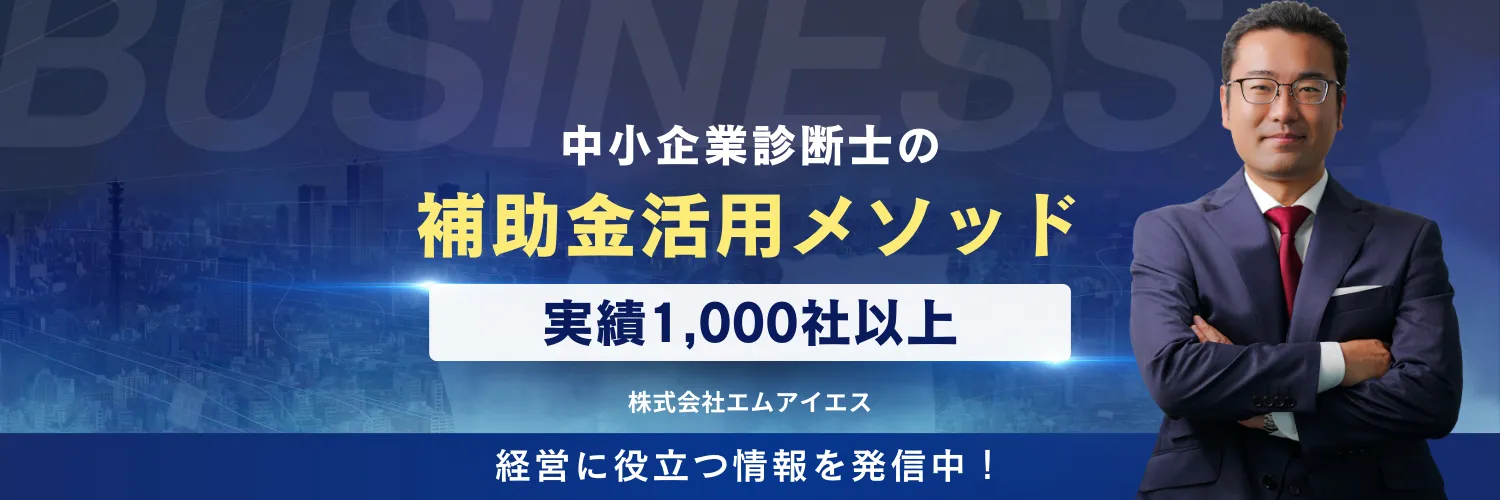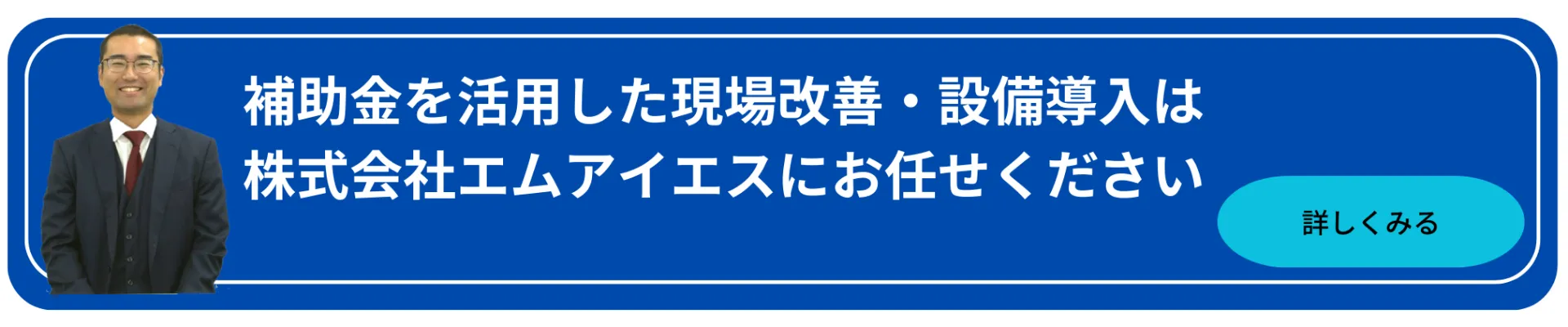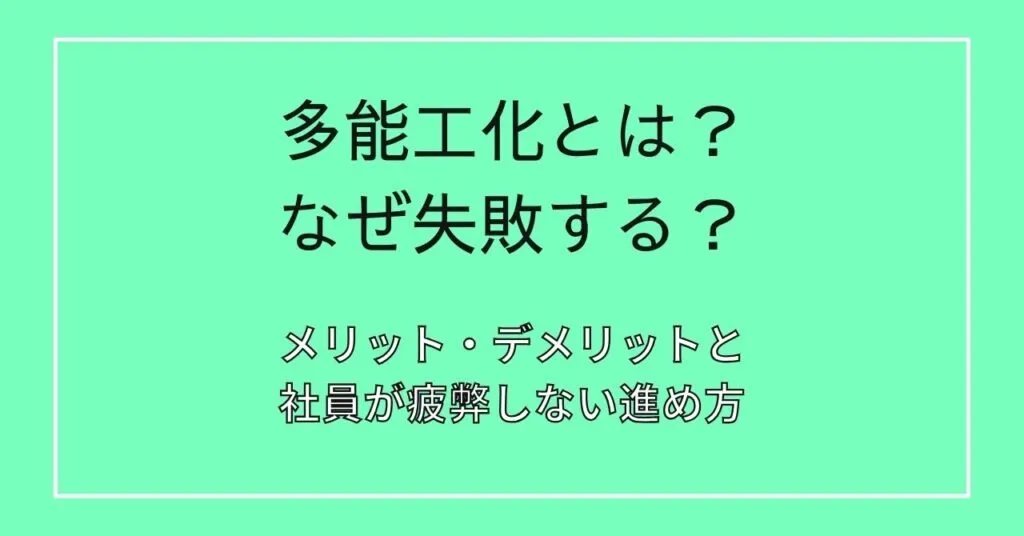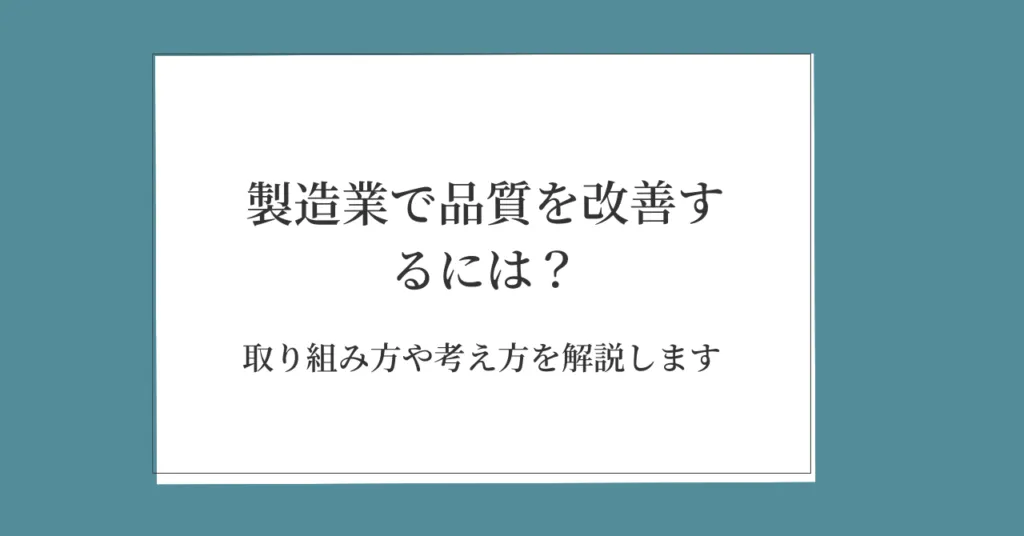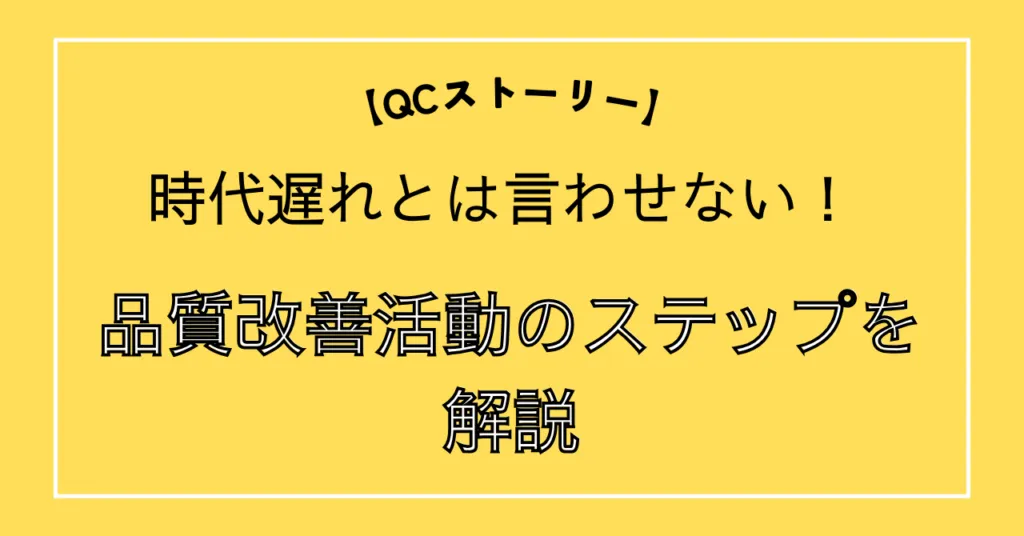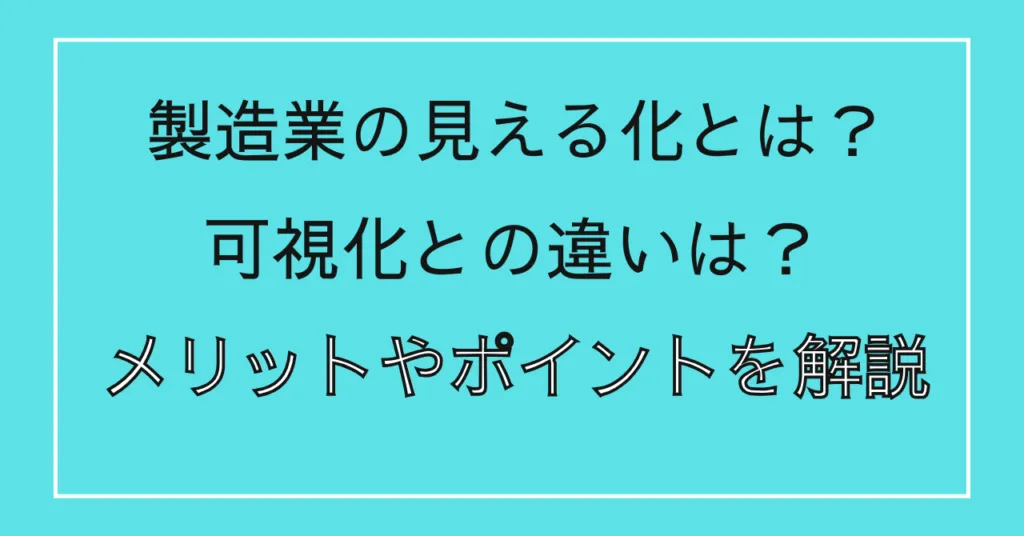【カンコツ作業】なぜ伝承されない?匠の技を標準化する方法を徹底解説!
2023/09/122024/09/11
「カンコツ」とはトヨタ生産方式の言葉のひとつで、「業務マニュアル化しにくい、熟練職人の技」を意味します。トヨタはカンコツ作業の標準化を徹底し、最終的に機械化することで、企業全体で高度な技術を獲得してきました。
中小企業においてもカンコツ作業の標準化は避けて通れません。この記事ではカンコツ作業を標準化する方法を中心に、カンコツ作業について徹底解説します。
カンコツ作業の伝承が進まない理由
現在、製造業において技能の伝承が大きな課題となっています。中でもカンコツ作業は匠の秘儀的な要素があるため、若手への伝承が難しいのが特徴です。ここではカンコツ作業の伝承が進まない理由を解説します。
カンコツ作業を標準化する方法
カンコツ作業を標準化することで、職場全体で技術を共有でき、生産性の向上が期待できるでしょう。ここではカンコツ作業を標準化する方法を解説します。
カンコツを含めた作業手順書を作成するポイント
作業手順書は標準化した作業内容を全員に周知するのに必要不可欠です。適切に標準化を行っても、作業手順書が適切でないと十分に周知徹底することが難しく、標準化の効果が薄くなりかねません。ここでは作業手順書を作成するときのポイントを解説します。
カンコツ作業を現場に定着させる方法
カンコツ作業を現場で活かすには、現場全体でのサポートやフォローが必要不可欠です。ここでは標準化したカンコツ作業を現場に定着させる方法を紹介します。
カンコツ作業がもたらすデメリット
カンコツ作業の内容自体は有益ですが、一部の人だけが技術を保有していることによるデメリットは大きいと言わざるを得ません。ここではカンコツ作業がもたらすデメリットを解説します。
カンコツ作業に関するよくある質問
最後に、カンコツ作業に関するよくある質問を集めました。カンコツ作業の標準化など日々の業務に役立ててください。
IoT技術をカンコツ作業の標準化に活かせますか?
IoT技術はカンコツ作業の標準化を行うにあたって非常に有益なものとなり得るでしょう。例えばアイトラッキングカメラという、人の瞳孔の動きをリアルタイムに検知してデータ化できるカメラを用いて、熟練社員が作業をするときの視線の動きを計測します。そのデータを標準化に活かすことで、より精度の高い標準化につながるでしょう。
保全分野では、センサーを使って肉眼では検出できない異常を感知することで、不具合が起こる前に対応できるようになります。熟練社員の「カンコツ」に頼っていた部分をセンサーで判断することで、機械による標準化が実現可能です。
IoT技術の導入で、カンコツ作業の標準化のみならず、ヒューマンエラー防止など現場のメリットは大きいでしょう。設備の導入には費用がかかりますが、「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」などの公的な補助金に採択されれば、費用削減が可能となります。
まとめ
カンコツ作業は高品質の製品を製造したり、さまざまなトラブルに対応できたりと、決して悪い面だけではありません。問題はそれを一部の人員だけで保有し続けることです。人員不足の今、このままだと貴重な技術が失われ、業界全体の低迷を招きかねません。
日本の製造業を世界で通用させるためには、熟練職人の技を受け継いでいく必要があります。カンコツ作業を後世に残すためには、カンコツ作業の標準化への取り組みが重要です。
株式会社エムアイエスの現場改善コンサルティングサービスは、大企業で現場改善歴30年以上のベテランコンサルタントが企業に出向いてアドバイスを実施します。
中小企業診断士が在籍しており、ただ現場改善をするのではなく、経営目線で役に立つ施策提案が強みです。
補助金獲得サポート経験も豊富にあるため、多くのケースで補助金・助成金を活用して費用を抑えることが可能です。
現場改善を検討しているけれど費用面でお悩みの方はもちろんのこと、機械導入のために補助金の活用を検討している方もお気軽にご相談ください。