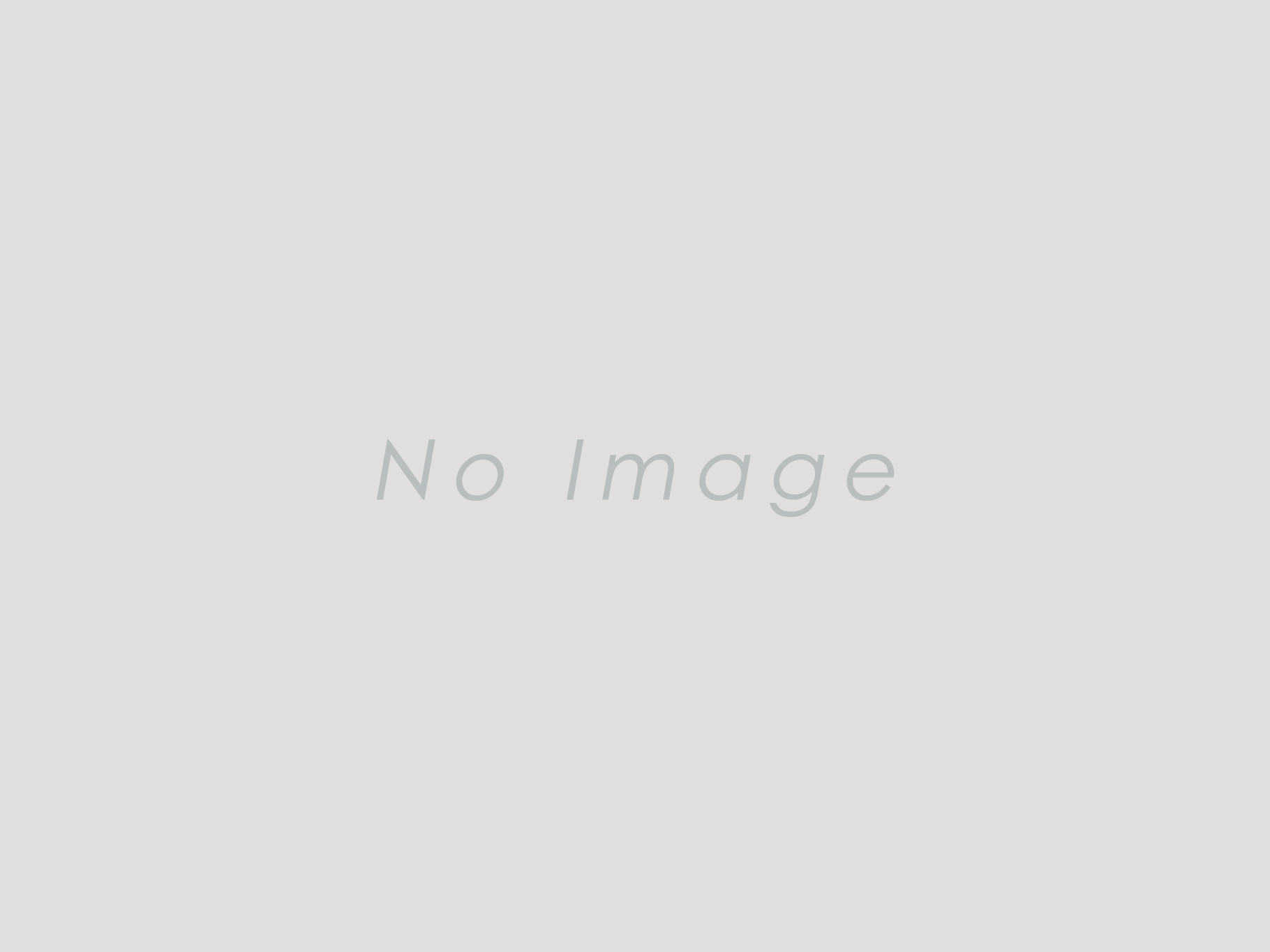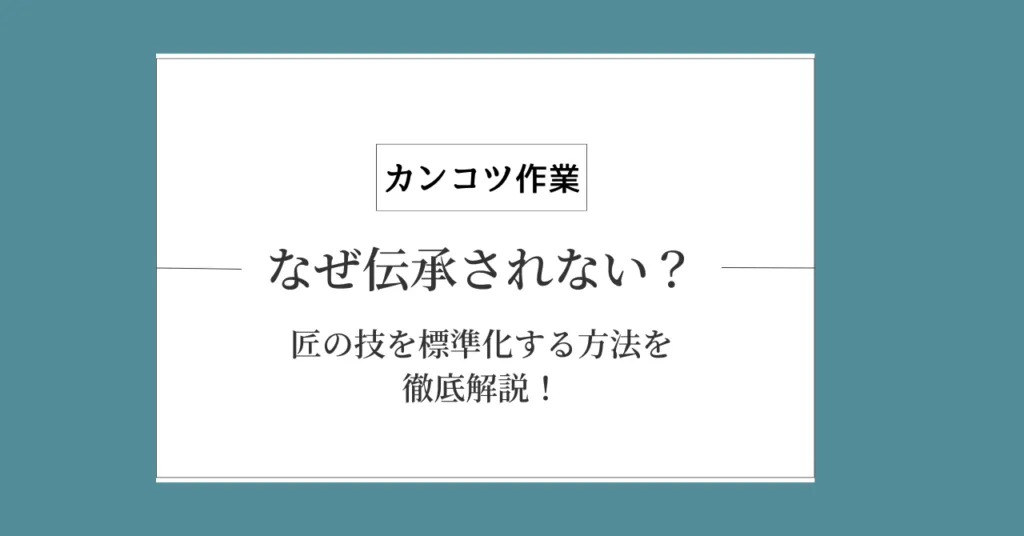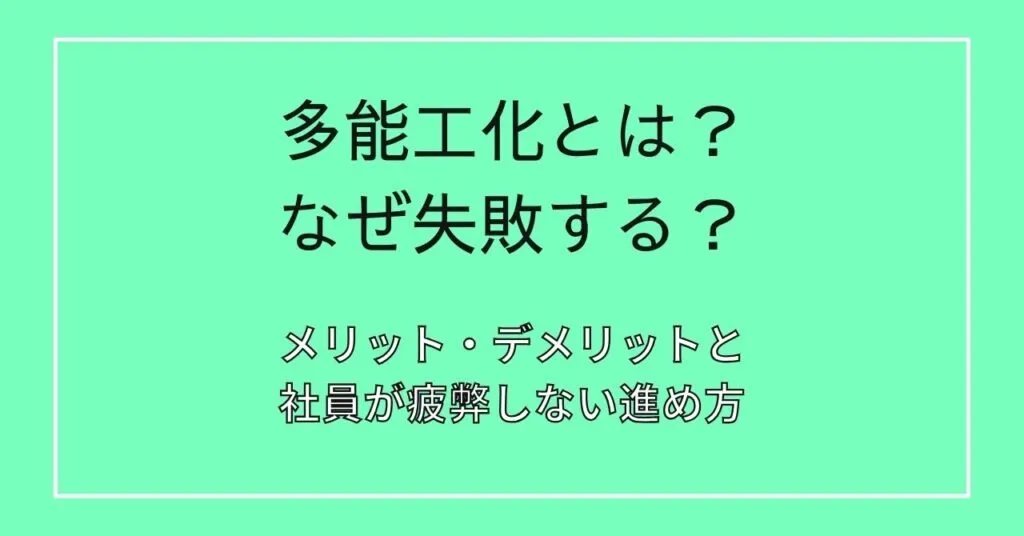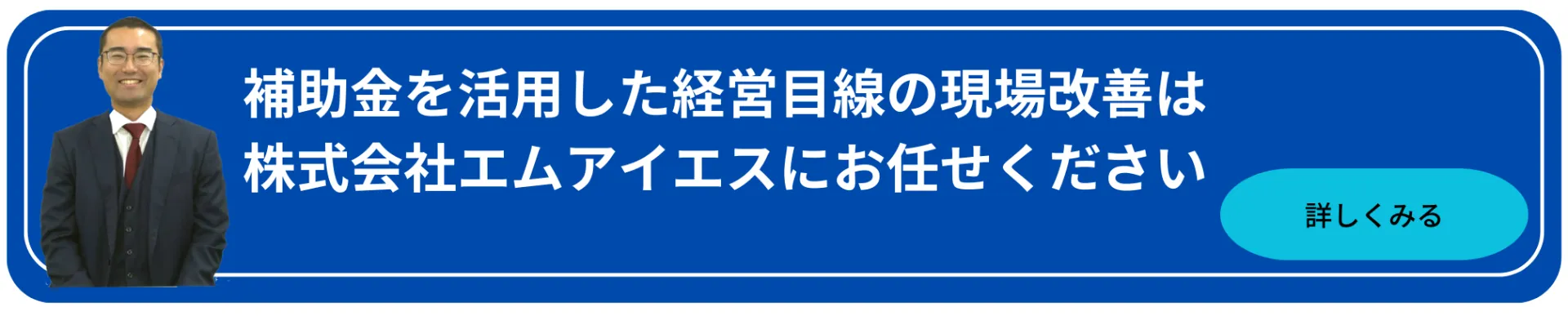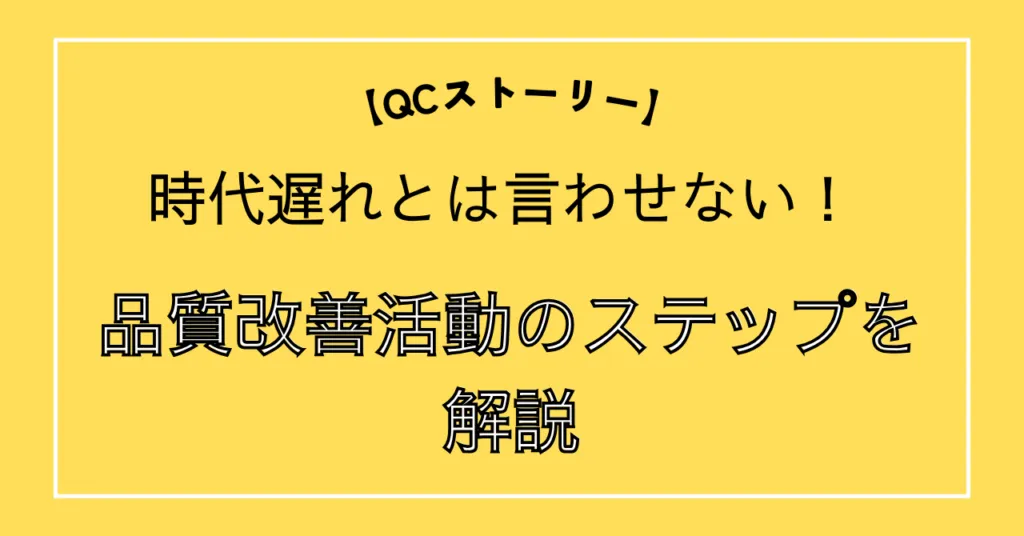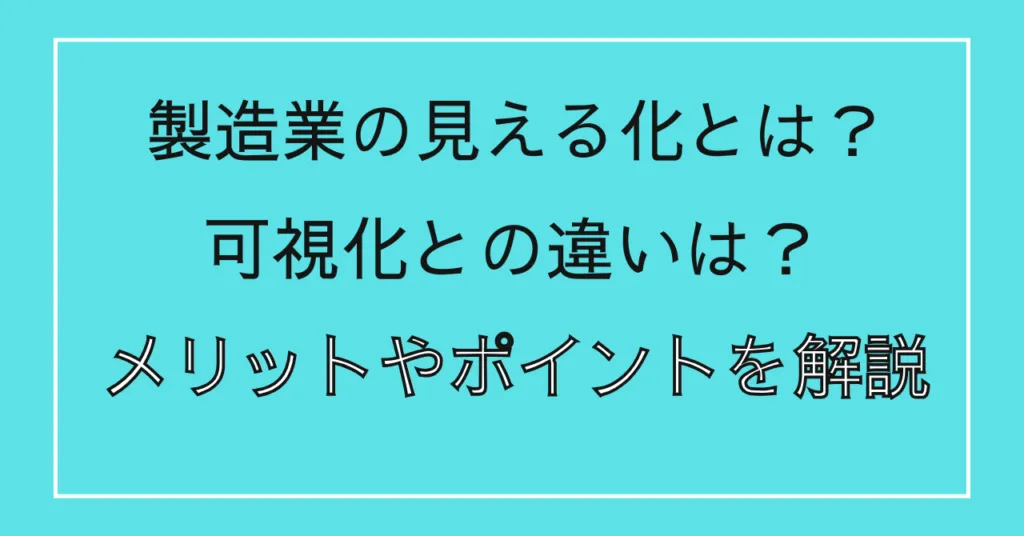製造業で品質向上をするには?取り組み方や考え方を解説します
2023/07/032024/06/10
製造業で働く上で、品質向上は避けて通れないテーマです。しかし大きなテーマであるため、どのように品質向上へ取り組んだらよいか迷うこともあるでしょう。
そこでこの記事では、製造業における品質向上について、概要や取り組み方、問題点を徹底解説します。品質向上に取り組む際に、参考にしてみてください。
目次
- 製造業の品質を決定する2つの要素
- 製品の品質
- 作業の品質
- 品質向上に重要な「5つの化」
- 可視化
- 定量化
- 課題化
- 実践化
- 定着化
- 品質向上を阻む要素
- 人手不足による業務の質低下や属人化
- 【カンコツ作業】なぜ伝承されない?匠の技を標準化する方法を徹底解説!
- 人手不足による業務の質低下や属人化
- 脆弱な管理体制
- 改善策に取り組むだけの組織体制
- 紙媒体やExcel管理による管理工数の増加
- 品質向上のための取り組み
- 5Sの徹底
- PDCAサイクルの導入
- QCストーリーの導入
- 業務のムダ・ムラ・ムリの見直し
- 業務の標準化
- 社員の多能工化
- 多能工化とは?なぜ失敗する?メリット・デメリットと社員が疲弊しない進め方
- 製造業の品質向上に関するよくある質問
- 4Mとは何ですか?
- TQMとは何ですか?
- ねらいの品質とは何ですか?
- まとめ
製造業の品質を決定する2つの要素
製造業の品質を決定する要素は、製品そのものの品質だけではありません。ここでは品質の良し悪しを決定する要素について解説します。
品質向上に重要な「5つの化」
「5つの化」とは経済産業省と株式会社日本能率協会コンサルティングが、サービス産業の生産性向上手法として提唱したもので、製造業の品質向上にもよく使われる手法です。ここでは「5つの化」の手順を具体的に紹介します。
品質向上を阻む要素
品質向上を実現するにはさまざまな要素が必要となるため、一筋縄ではいかないこともあります。特に人に関わる問題や職場の体制は大きな壁となる傾向があるでしょう。ここでは品質向上を阻む要素について説明します。
人手不足による業務の質低下や属人化
社会問題となっている人手不足ですが、製造業も人手不足の影響を大きく受けている業種の一つです。人手が足りないと、目の前の作業を終わらせるのに精一杯で品質のことまで対応する余力がない傾向にあります。
現場の人手が不足すると発生しやすいのが属人化です。特定の業務について作業員全体で共有する余裕がないと、ノウハウを一部の人しか知らない状況が発生します。せっかくよい技術を持っていても活用される機会が少ないため、品質向上を阻む要因となるでしょう。
属人化の原因にもなる「カンコツ作業」について下記の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
品質向上のための取り組み
「5つの化」以外にも品質向上のための手法はいろいろあります。自分の職場に合った取り組みを採用することで効果的な品質向上が可能です。
ここでは品質向上のための取り組みをいくつか紹介します。
ムダ | 能力に対して負荷が小さすぎる作業、付加価値を生まない作業 |
|---|---|
ムラ | 材料やマンパワー、忙しさなどにバラつきが大きくムラのある状態 |
ムリ | 能力や状態に対して負荷が大きすぎる無理な作業 |
多能工化の方法について下記の記事で詳しく説明しています。併せてご覧ください。
製造業の品質向上に関するよくある質問
最後に、製造業の品質向上に関するよくある質問についてまとめました。品質向上を進める上でぜひ参考にしてください。
まとめ
品質向上をするためには的確な計画、実行力、状況に合わせた柔軟性が必要です。そして何より重要なのは、一人一人が当事者意識を持ってメンバー全体で目標や計画を共有することに他なりません。
それぞれの工場で課題と強みがあるため、強みを活かしながら課題を改善できる施策を打ち出すのがベストです。些細なことでも改善すれば品質向上につながります。日々の気付きを活かして品質向上に取り組んでみてください。
株式会社エムアイエスの現場改善コンサルティングサービスは、大企業で現場改善歴30年以上のベテランコンサルタントが企業に出向いてアドバイスを実施します。
中小企業診断士が在籍しており、ただ現場改善をするのではなく、経営目線で役に立つ施策提案が強みです。
補助金獲得サポート経験も豊富にあるため、多くのケースで補助金・助成金を活用して費用を抑えることが可能です。
現場改善を検討しているけれど費用面でお悩みの方は、ぜひご相談ください。